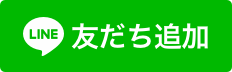6年生が残り3か月でやることリスト
こんばんは。
中学受験コンサルティングタカベルの高畑です。
いよいよ本番まで残り3か月となってきました。そこで、最終盤に6年生が積み上げていくとよいことと持っておくべき意識について記したいと思います。
・本番を見据え、朝学習の習慣がついていないお子さんは朝型に生活リズムを整える。
入試は朝に行われる。
・計算ミスはミスではなく、失点と捉える。ここができていれば、合格最低点にのったと計算ミスを軽く捉えていると、本番で痛い目にあってしまう。練習でできないことは本番ではできるようにならない。
・算数の過去問の点数が全くとれない場合、今の時期でも単元の学習に戻るべき。
特に序盤の小問クラスでも手がつかない場合は、5年生の最初に習った教材まで立ち返る。
・考え方を書きなさいというタイプの解答欄は答えが間違っていたとしても、何かを書けば部分点がもらえる学校が多い。1点が合否を決めるので、少々わからなかったとしても、式でなくて、図でも言葉でもよいので何かを書くクセをつける。
・国語は時間配分が命。読解問題が1題の学校~3題の学校までと幅広いので、各学校の戦術を頭に入れてから、演習に入る。
・漢字と言葉と語彙の3点セットは引き続き、毎日の学習計画に入れていく。読解が安定しないお子さんでもここの領域が安定してくることで、大崩れは避けられる。
・詩や俳句の解説文を出題する学校もある。表現技法やルールについて、原理原則からもう1度確認をしたい。
・自由作文を出題する学校もある。学校はやってきた内容を見たいのではなく、本文に即した体験になっているのか、聞かれていることに相対しているのか、日本語の使い方は適切なのかを見たいだけなので、練習を積んで題材のレパートリーを広げたい。結論→具体→結論で書いていくことがおススメ。
・理科の知識は生物・地学分野を中心に学習を進めがちだが、化学分野も知識を聞いてくる学校は多い。空気より軽いのか、水にとけやすいのか、酸・アルカリ、試験薬、密度、集め方など。
・昨今のトレンドはなんといっても表とグラフ関係。塾の特化型演習教材や市販の教材で補強をしていきたい。ここが最近もっとも差がつく単元といってもよい。
・意外と盲点なのが実験器具の使い方。星座早見・顕微鏡・ガスバーナーなど、勉強が甘くなりがちな範囲こそ、差がつく。
・物理と化学計算に苦手を抱えている場合、算数と同様、基礎に立ち返ることがまだ重要。
・最もまだ伸びしろあるのが社会。特に1月は社会の学習比率を高めることが吉。
・3か月前の段階は時事問題よりもまだ知識の積み上げ。焦らない。
・差がつくポイントは統計資料・雨温図・年表・史料・憲法・表とグラフ。
・過去問学習が進んできたと思うので、過去問を進める日と振り返る日を設けるとよい。
過去問の解きっぱなしは危険。
まとめ:算数と理科の基礎が抜けている場合、まだ入れ直してよい段階。
知識系は今からでもまだ間に合う。
入試は1点勝負なので、ミスは言い訳にせず、差が付きやすいところをつぶしていく。