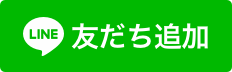第一志望合格者から見る6年生社会の勉強法
こんにちは。
中学受験コンサルティングタカベルの高畑です。
先日、視察もかねて、オンライン自習室の監督を1日体験してみました。
今の子たちはすごいなと感心させられました。周りの目があっても概ね集中して取り組むことができていました。
せっかくやる中学受験ですから、自らやることを考え、それを実行に移すPDCAサイクルを回せたら、より意義深いですね。
親御さんがお仕事で不在な中でも、皆さん大変立派でした。
ちなみに、当オンライン自習室は金曜日には質問対応しているのが売りです。本日は当該日。積極的な質問を期待しております。
さて、本日は今回の入試で第一志望校に合格された子がどのような勉強をしていたのかシリーズ。
6年生社会編です。
まず、社会が他の科目と違う特性があることを記したいと思います。
他の3科目は概ね中学受験に必要な新出単元を5年の段階で終えています。しかし、社会だけは新出単元がまだ進みます。
なので、公民の学習をメインに進める必要があるのですが、4月の合不合や首都圏模試では地理や歴史も当然、出題があります。
そして、6年生後半からでもまだまだ新しくやることがあるのが社会の特性です。
そこで、しっかりとした学習計画が求められます。
6月頃まで→毎週の新出単元のキャッチアップ+4まとやコアプラなどの1問1答を5割の精度を目指す。
7月・8月→4まとやコアプラなどの1問1答を8割の精度で。
9月→統計資料や年表や史料などの細かい部分を5割の精度を目指す。
10月・11月→過去問演習+グラフの読み取り・記述・地形図対策を同時並行で。
12月・1月→過去問演習+時事問題
社会は9月以降にも行うことがまだまだあります。そして、9月以降で最も伸びを見せるのが社会です。
したがって、8月までは欲張らずに新出単元のキャッチアップと1問1答を8割の精度に仕上げることを第一目標に頑張っていきましょう。
そして、9月以降に志望校に応じて、統計・年表・史料・グラフ・記述・地形図などの1問1答以外を進めていく。
大切な視点は模試の結果を気にしすぎ、前期の学習比率のバランスを崩さないこと。
前期は算数と国語です。
後期は徐々に社会の比率を増やしていきます。
上記の見通しに基づいて、計画的に学習を進めていきましょう。
※「社長の履歴書」さんより、取材を受けました。ぜひご覧ください。