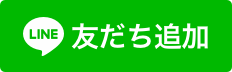6年生後期の指針
こんにちは。
中学受験コンサルティングタカベルの高畑です。
本日はこれから訪れる6年生後期の指針について、まとめてみたいと思います。
①親御さんの最も大切な仕事はメンタルケア
ここからの6年生の親御さんの最も大きな仕事はお子さんのメンタルケア。 毎月受ける模試・過去問でお子さんは立ち位置が否が応でも分かります。やらなきゃマズイという意識も自ずと芽生えてくるものです。マイナス言葉をかけても良いことはないどころか自信を失ったり、テストに恐怖感を覚えるなど、事態はより悪くなるので、とにかくノセる、励ます。6年生の親御さんには不安や焦りは私にぶつけ、お子さんにはぶつけないように伝えています。
②過去問は戦略をもって
私達の過去問に対する考え方は戦略立案と反省点のあぶり出し。 二度と同じ問題は出ない可能性が高いが、時間配分や傾向を体に染み込ませるという目的で過去問は重要。 稀にしか出ない難問のやり直しに時間をかけて注力する方向ではなく、大問2番までは◯分、(3)は全ての大問後回し、生物→地学→物理→化学の順番に解くなど、戦略をもって過去問学習を進める。過去問分析プランでこのあたりをガンガン情報提供していきます。 そして、過去問直しノートに「今回の反省点」をまとめておき、次回同じ学校の過去問を解く時に「意識しなければならないポイント」を添える。 次に過去問を解く時に、前回まとめた「意識しなければならないポイント」を確認してから、問題に取り組む。 最初に点数が取れないのはこの戦略が定まっていないから。解く中で徐々に点数が上がっていくのは要領をつかんできたからです。
③消化不良との戦い
例えば、SAPIX生は平常・土特・SS・過去問と飽和状態に陥ります。 復習の優先順位をつけることが大切です。 例えば、SS>過去問>平常>土特 という具合に、 間違っても全てをこなそうとしないことが重要です。 前述の通り、過去問はその学校が求める人物像に近づくトレーニングなのでとても大切です。 過去問から判明した苦手分野を放置していると、求める学校の人物像には近づけません。 しかし、時間は有限です。学校も始まります。 10のタスクを5割の理解度で進むなら、5のタスクを8割の理解度で進むという心持ちで進めていきましょう。 これは科目ごとに落とし込んでも、同じことが言えます。 四谷生・早稲アカ生で算数が50以上あるお子さんは予習シリーズ下巻の「1行問題ベストセレクションステージ1」と「演習問題集★1」はカットするなど、メリハリをつけて学習を展開していきましょう。
長くなりましたが、
・メンタルケア
・過去問の戦略と反省
・塾タスクを絞る
この3点に注力していきましょう。 私共も9月からは5ヶ月ノンストップで、過去問分析対応とスケジュール作成に追われます。1人1人に最適なプランと戦術を授けて、全力でサポートします。