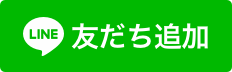テストで強い子にするには
こんばんは。
中学受験コンサルティングタカベルの高畑です。
今回のテストは完璧に準備した。親としても手ごたえがある。
しかし、結果は、、、
こんなことあるかと思います。
準備してきたことは本番で6掛けになると思っておくと肩の荷もおりるかと思います。
本日は6掛けを8掛けにするエッセンスを紹介します。
✅ 最初の問題こそ慎重に
本番で力を発揮できていない子の特徴は序盤の失点。
人間の心理として、最初の方の問題は無意識に「早く解こう」という意識が働いています。簡単だし、後にたくさん問題が待っているから。しかし、序盤の失点を後半の問題で取り返すことは大変です。しかも、算数の模試はどの問題も配点が同じであることが多い。そうなると、後半でとるよりも序盤で落とさない方がはるかに重要なわけです。
序盤の問題こそ、「途中式・筆算・丁寧に」これを合言葉にさせましょう。
✅ 大まかに時間配分を
1題の問題にのべつ幕なし時間をかけると、当然ジャブのように後に響きます。
特に理系志向のお子さんに多いのですが、手掛かりがつかめそうでつかめない問題に時間をかけすぎてしまう。日頃の家庭学習では問題ないのですが、テストは制限時間が常につきまといます。国語が最たる例ですが、読解1題にかけられる時間は約23分。これに30分レベル費やすと、残りの大問1題をゴッソリ失点します。150点満点の模試で、1題の読解をゴッソリ失点すると、60点弱もっていかれます。60点中の平均点が30点だとしても、30点他科目でカバーは至難の業。大まかに時間配分を入れて、臨みましょう。
✅ 制限時間付きトレーニング不足
これは賛否が分かれるところですが、家庭学習は基本的に丁寧が望ましいというスタンスです。ところが、テストでは丁寧すぎるのも考え物。折衷案が難しい。
そこで、テスト1週間前は計算学習に制限時間付きトレーニングを入れてみるなどをするとよいでしょう。組み分けやマンスリーは大体、50分で30問。5問は捨て問としたら、1問2分。計算を1問2分で解く練習をするとよいかなと思います。あくまでも目安です。個人差は考慮していないので、悪しからず。
✅ 解く順番を決めておく
テスト範囲は4単元。仕上がりが盤石な単元もあれば、そうでない単元もあるでしょう。
当然ですが、得意な題材で時間切れを起こしてしまうのは大変もったいない。そこで、ある程度捨ての単元が出たら、後回しにするなどのルールを決めて、臨むとよいかと思います。
私は小学生のころ、立体図形がまるでダメだったので、立体は完全に後回しにしていました。
ムムム、後回し?もはや解いてなかったかなと笑
✅ クラスや偏差値を意識させない
たまにテスト前日は眠りが浅くなるというお子さんがいます。子どもは子どもなりにどんなに小さいテストでも、「テスト」と言われると身構えるものです。そこに、「次は〇クラス入りたいね」や「偏差値50は絶対だよ」などと、言葉をかけると余計萎縮します。
そんなお子さんには、「100%の力を発揮してきてくれたらうれしいよ」や「50分手を止めないできてくれたらお母さんは100点をあげるよ」などの言葉がけで、プレッシャーを極力取り除いてあげましょう。
✅ テスト直前は得意単元を伸ばす
まれにテスト前日に弱点補強を行うケースを目にしますが、これは逆効果です。
そもそも、テストまでの1か月に克服できなかった弱点が1日でクリアになるわけがありません。それはまさに付け焼刃。
だったら、テスト直前はよいイメージを持たせるためにも得意単元を伸ばすことに注力した方がよいでしょう。極端な話、得意な科目1科目だけを行うということでもよいかもしれませんね。
まとめ:練習でできないことは本番ではできない。
練習でできたことは本番でできるとは限らない。
なぜなら、時間と心がテストでは大きな要素だから。