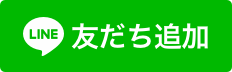本番を戦う前の受験生への言葉がけ
こんばんは。
中学受験コンサルティングタカベルの高畑です。
いよいよ今週から本格的にスタート。
受験生をお持ちのご家庭は体調管理をはじめとし、気の休まらない日が続いていることかと思います。
それもあと1か月です。もうひと踏ん張りですね。
さて、本日は本番を戦う前に伝えておくとよい受験生への言葉がけを列挙したいと思います。
ご参考になりましたら、幸いです。
✅ 1分1秒たりとも手を止めない
✅ 周りを気にしても点数は上がらない
✅ 行きたくなくても科目間と試験前はトイレに行く
✅ 科目間は勉強しない
✅ 分からない問題はみんなもできていない
✅ 100点を取る戦いではない
✅ 算数17点でも合格している子はいる。4科目で合否は決まる
✅ 科目間はルーティーンワークを1つ
✅ 何かアクシデントがおきたら、必ず手を上げる
✅ 入りたいという想いを解答用紙にぶつける
✅ 知り合いを見つけても、話しかけない。今日だけはライバル
~まとめ~
入室したら、親御さんができることはもうありません。
11歳・12歳のお子さんが1人で戦う舞台。
大切なことは不安な気持ちを最大限取り除いてあげることと100%の力を出させてあげること。
最初の科目でつまずいても大丈夫。
みんなできているわけではない。
とにかく手を動かす。想いは伝わる。
アクシデントは大人を頼る。
トイレに必ず行く。
このあたりを親御さんなりの言葉で送り出してあげてください。
最大の味方は親御さんです。