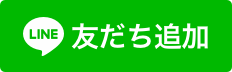こんばんは。
中学受験コンサルティングタカベルの高畑です。
国語の制限時間が無限であれば、大きく差はつかないでしょう。
国語で差がつく原因の一番大きなポイントは「制限時間」があること。
そこで、読むスピードの遅いお子さんが無意識にやっていることを明示しますので、これを行わないという視点で日頃の学習にいかしていただければと思います。
✅ 意味の分からない言葉が出てきたときにフリーズ
文を読み進めていく中で、意味の分からない言葉が出てきたときにフリーズをするお子さんがいます。経験上、まじめなお子さんほど見受けられる傾向です。考えても答えは出てこないのと、聞かれないことの方が多いので、スキップしましょう。
✅ 無意識のうちに返り読みをしている
大前提として、どんなに国語力の高いお子さんでも試験問題を2回読むことは時間的に不可能です。1回で決めなければなりません。音読トレーニングをやらせるとわかるのが、同じ行を繰り返し読んでしまっているお子さんが6年生でも散見されます。であるからこそ、音読トレーニングは重要なのです。
✅ 主語と述語に注目していない
世界各地で大きな影響を及ぼしている地球温暖化は二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)など人間の活動によって増加する温室効果ガスによって引き起こされる。
たとえば、こんな文章があったとします。
要は、「地球温暖化は温室効果ガスによって引き起こされる」が言いたいわけですね。
修飾語はあくまでも飾り付け。文の骨格は主語と述語です。
✅ キーワードに注目していない
論説文は特に、タイトルに目を通してから解くとよいでしょう。筆者が主張したいことがタイトルになっている可能性が非常に高いです。そして、文中に繰り返し出てくる言葉はキーワード。キーワードに注目をして読み進めていくと、その段落で言いたいことがクリアになります。
✅ 本文の肝を押さえていない
物語文であれば、行動・表情・情景描写などによって描かれる心情。
論説文であれば、接続語・指示語・問題提起・主張。
国語の先生が聞きたいポイントは大抵同じです。聞き方が記述なのか選択肢なのか抜き出しなのかの違いです。
本文で大切なポイントを可視化できていれば、問題を解くときの時間短縮につながります。
✅ 文を塊としてとらえていない
スピードの遅いお子さんや苦手なお子さんは、文を1文1文でとらえて読もうとします。
これを段落ごと・場面ごとにとらえる練習をしていきましょう。段落ごとに小見出しをつけてみるとか、場面ごとに心情を要約してみるとか。国語こそ、家庭学習のやり方がもろ点数に直結します。
ご参考になりましたら幸いです。
特に5年生のご家庭は学習時間の太宗を理数科目にもっていかれてしまい、国語まで手が回らないというご家庭も多いかと思います。
漢字と知識の学習のみに留まってしまっているというお話も多く頂戴します。
範囲の決められたテストで成績を追い求めるという視点ではどうしてもこうなりがちです。
しかし、入試本番での国語の配点の価値の高さと国語はどうしても他の科目にも通ずる学習なので、1日10分でも15分でも取り組んでみることを推奨します。
1日10分でも1年間毎日ならば、年間で60時間。
そして、なにも読解問題を「解く」ということをしなくても構いません。
時間がないときは、
① 読解に必要な語彙の意味を10個マスター
② 主述に注目しながらの読解の音読
③ 読解題材の線引き
④ 読解題材の要約や小見出しづけ
⑤ 短文要約教材
⑥ 選択肢や記述の解法に関する参考書を読む
のいずれか。
宿題を闇雲に済ませるよりも1日10~15分と決めて、①~⑥のいずれかを行うだけでも1年間で大きな貯金となります。
基本的に苦手科目や分野に取り組むときは、ダラダラ長時間よりもスパッと短時間毎日が鉄則です。
2025年12月23日 10:39