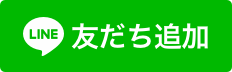5年生意外とやっておいた方がいいことリスト
こんばんは。
中学受験コンサルティングタカベルの高畑です。
いよいよ6年生も入試に突入。
5年生はまもなく受験の最高学年に。
重点復習回は以前のブログで挙げたので、それがある程度クリアになっている方向けにアップデート。
✅ 数3兄弟(場合の数・数表等の規則性・数の性質)
✅ 語彙力強化
✅ 理科の表とグラフが絡む問題
✅ 白地図と年表
重要単元のキャッチアップが忙しくて上記は後回しになりがちですが、特に場合の数は非常に差が付きやすく、しばらくの間ご無沙汰になっている単元。
場合の数はできなくても他の領域に影響しないので後回しになりがちですが、克服に時間のかかる要注意単元。
国語は語学。
日本人が英語を学習するときに膨大な単語テストを課されるのは、知らないと読めない・書けないから。国語の読解と記述もテクニカル的要素を除けば、究極は語彙力の勝負。
日本の英語教育同様、読みと書きが求められる勝負では語彙力は必要不可欠。
昨今、5年生の首都圏模試でもその言葉をしらないと切れない選択肢が出現傾向。
理科のトレンドは表とグラフ。
指導要領改訂の影響で算数にデータ活用が下りてきたように、表とグラフの読み取りの能力は私立でも必須となっている。算数と理科が得意でも表とグラフが出るとダメというお子さんもいるので、トレーニング必須。詳しくは追々。
社会はご無沙汰になっている地理と知っておけば大変有利な年表。
来る4月の合不合をはじめとする模試では普通に半年以上やっていない地理もで出る。
手っ取り早く網羅的に確認できる教材は白地図。
そして、年表。
5年の組み分けレベルでも時系列を聞いてくる問題のオンパレードなので、やっておくと得。
しかし、これらは最重要単元のキャッチアップが済んでいることが前提です。上記まで手が回らなくても問題ないので、ご安心ください。