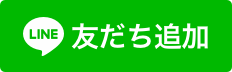各偏差値に応じた国語の課題(YN偏差)
こんばんは。
中学受験コンサルティングタカベルの高畑です。
以前の記事でも紹介させていただきましたが、時間が空きましたのでアップデートをいたします。
あくまでもご参考かつ一般論ということで。
40以下→語彙力、集中力、音読練習、漢字と知識
45以下→語彙力、精読力(重要部の可視化と要約練習)
50以下→語彙力、速読力、時間配分(片方の題材が解ききれない)
55以下→語彙力、題材への経験値(特定の題材になると成績が落ちる)
60以下→語彙力、解き方(選択肢の切り方、記述の書き方の型)
65以下→語彙を使いこなし、自分で言い換えて記述する力
国語は語学なので、語彙力の積み上げはマスト。
英語を学ぶときにひたすら単語テストをされるのと同様で、語彙力がなければ、書くことも読むこともできないため。
ただ、英語と決定的に違うのが、英語の単語テストはりんご→appleなのに対して、語彙の勉強は葛藤→心の中の相反する感情という具合に、意味をしっかりと理解することが大切。
例文を作るとか、イメージしやすいように例文を語ってあげるなどが有効。
次なる壁が精読。
国語が他の科目と決定的に違うのが、勉強してきた問題が本番では変わること。
つまり、やみくもに宿題の問題だけを解いていても、その問題では通用するがという現象が発生。どの文章になったときにも通用するように基本作法をおさえることが大切。
そのために線引きや要約練習というアプローチがある。
これができた上でのスピード。
そもそも重要な部分がどこかが分からなければ、どこを流し読みしてよく、どこが答えにはならないのかが分からない。スピードと精読練習は相反するように思うが、速く読めるようになるために精読が大切。
さらなる壁が題材への経験値。
恋愛話になると崩れる、哲学的題材になると崩れるという現象。
ここで初めて読書の大切さが出てくる。推薦図書や各学校の出典をチェックすることは重要。先日紹介した「あんずとぞんび」は他者理解という時代のトレンドを反映した1冊なのでおすすめ。
でも、そんな時間はとれない。
だからこそ、テキストを精読・音読という前段階の学習がここでも活きてくる。
あの時の主人公の心情は何がきっかけでどう移り変わっていたのか。その経験値が題材による成績のブレを一定程度防ぐことができる。
ここまでベースを整えてから、「解く」。
物語の選択肢問題は後半部でまずは切るとか、論説文の傍線部は1文に伸ばすなどのテクニカル的要素は間違いなく知っておいた方が得。なのだが、やはり前段階のベースがないと、テクニックに終始してしまう。
なので、最悪の勉強法は宿題を解いて終わりという状態。
望ましい勉強法はこつこつと語彙を積み上げ、音読と精読をおこなってから、問題を解く。
1日に全部を家庭学習でやると嫌になるので、塾なし日に日割りで少しずつ進める。
「ローマと国語は1日にして成らず」です。