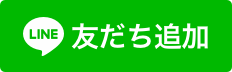短期的目線vs長期的目線
こんばんは。
中学受験コンサルティングタカベルの高畑です。
最近、人生でも中学受験でも葛藤していることがあるので、一筆記します。
目先のお金や生活や成績や楽しみって非常に重要なのだけど、ふとした時に5年後の自分のこととか将来の自分ってどうなっているのだろうと、考えるシーンってありますよね。
私みたく、銀行や学校という世間では比較的安定の仕事に従事していたころは、目先のことを考える毎日でよかったのですが、ふとした時に30年・40年働き続けることってできるのだろうかと常に葛藤していました。
そして、小さいながらも自分で会社を経営するようになって、より長期的目線が求められるようになったと感じる毎日。ひょっとしたら自分自身が明日倒れるかもしれない。倒れたら、周りに迷惑がかかる。だから、減量をして体を絞るなど、長期から逆算して行動を決める。
そう考えると、目先のことよりも常に頭に浮かぶのが1年後自分はどうなっていたいか、3年後会社がどういう状態になっていてほしいか。それに向けて色々と手を打つ。
中学受験でも常にこの2つの目線ってつきまとうと思います。
子どもも親御さんも短期の成績で心は安定し、モチベーションは高まる。
しかし、短期での成績を上げることと長期での成果を上げることは似て非なるもの。
DCや週テストではとれるけど、マンスリーや組み分けになると取れなくなる現象に近いかなと。
中学受験ってすごく特殊で、行きたい学校と理解度は子どもそれぞれ。
付け焼刃で短期の成績を上げること自体は難しくないけど、それが長期での持続的成果になるかどうかは本当に人それぞれ。そして、行きたい学校によっては不要な短期の勉強もある。
なぜなら、付け焼刃で習得した内容はすぐに忘れるし、中学受験のカリキュラムはどの学校にも対応できるように作られているから。
でも、短期の成績を求めなければ、子どものモチベーションも上がらない。
うーん、だから中学受験は難しい。
折衷案というわけではないが、親御さんが長期的視野をもっておけばよいのかなと。
今4年生だけど、5年生の後期になったらこの関門が待っている。
だから、4年生で習っているこの単元はしっかりと理解させるまでやらせようとか。
今5年生だけど、6年生になったときにあわてないように早めに志望校案を組んでおこうとか。
親御さんがお子さんの短期的成果を応援しつつ、長期的視野というロードマップももっておく。
たまに実家に帰った時に親がよく言うのは第二子のあんたの中学受験は楽だったよと。兄で経験して大体わかったから、と。兄の時は常に不安が付きまとい、やらせすぎてしまったようです。子育ての中での一番の後悔のようです。
今後とも、こうした長期的視野という類の発信を心掛けて、頑張ります。
11月は仕事にプライベートに最も忙しい1か月にする!
自分でも大切なことを見つめ直すために、記してみました。