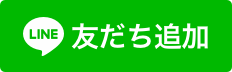2024年度合格実績
こんにちは。
中学受験コンサルティングタカベルの高畑です。
2024年度の中学入試の戦いはまだ続いていますが、一段落を迎えたころであると思います。
まずは、合格を勝ち取れたご家庭は本当におめでとうございます。
ここに至るまで様々な困難や気苦労が絶えなかったことであると拝察いたします。
ご本人をはじめ、受験に向かって多大なるサポートを行ったご家族の皆様には本当に頭の下がる思いです。
また、思うような結果が出なかったご家庭も中にはいることでしょう。
しかし、人生は思うような結果が出ないことの方が多いと常々思います。
かくいう私もそうでした。
銀行員の時は、最初の支店と転勤先の支店で求められることが倍になり、成績がふるわなかった時期もありました。
中学受験の時も、挫折の時期の方がはるかにはるかに多かったです。
今の仕事でも、テストがあるたびに毎回毎回成績アップにつなげられているわけではありません。
多少はあれども、私はこうした挫折のたびに悔しさを抱きます。
ですが、悔しさを経験しなければ、人間として成長していきません。
なぜなら、悔しさを経験すれば、次成功をつかむためにどうしなければいけないのかを真剣に考える機会が与えられるからです。
機会は言い換えれば、チャンスです。このチャンスは悔しさを経験した人にのみ、与えられるものです。
その悔しさをわずか12歳で経験できたことは尊く、貴重な経験であったことと思います。
今回の中学受験の経験を通じて、学んだこと・感じたことをどう生かしていくか。これに尽きると思います。
思うような結果が出なかったとしても、お子さんは確実に成長を遂げましたし、今後の長い人生において唯一無二の経験ができたわけです。プラスに捉え、中学での活躍を見守っていきましょう。
私たちの企業理念は「後悔しない中学受験を」をモットーに運営しています。
どういう結果であれ、中学受験が終わったときに「やりきった」「走りきった」という想いで、今後の人生を歩んでいってもらいたい。こう思っています。
結果は時の運も左右します。当日の体調、生まれた年による志願者の増減、問題の傾向変更元年など…
ですが、「やりきった」「走り切った」という想いは運とは関係なしに、頑張った分だけ味わえるものです。そして、今後も成功体験として、圧倒的自信につながります。
わずか12年しか生きていない子が人生の4分の1以上の期間を費やして行うのが中学受験。
多くの娯楽や時間を犠牲にする分、得られるものは合格以上に価値の高い宝物です。
私共もこの理念を常に忘れることなく、2025年度生(4期生)のサポートを今日から開始していきたいと思います。
2024年度合格実績(2月6日9時現在)※五十音順
・浅野
・アレセイア湘南
・市川
・浦和明の星
・大宮開成
・開智所沢(A特待)
・海陽学園
・カリタス女子
・吉祥女子
・京華(特選)
・埼玉栄(難関)
・栄東(東大難関)
・女子学院
・白百合
・頌栄
・巣鴨
・逗子開成
・聖光学院
・成城学園
・聖望学園
・高輪
・中大付属
・名古屋
・南山男子
・武南
・三輪田学園
・盛岡白百合
・早稲田佐賀
・和洋国府台
※書籍プレゼントキャンペーンを2月12日(祝)まで実施中です。
ご興味のある方は、HPよりお申し込みください。
※合格体験記は随時アップいたします。