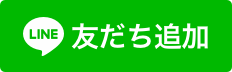こんにちは。
中学受験コンサルティングタカベルの高畑です。
4月のSO・合不合判定・実力判定・首都圏模試などの各模試に向け、6年生は志望校ラインナップを記載しなければならない頃かと思います。
また、5年生以下も5月から続々と学校説明会が始まりますので、選定を行わなければならない頃かと思います。
下記を前提条件としたお子さんをもとに、見ておくべき学校のラインナップを解説していきます。
・6年生
・5年1月の志望校判定の偏差値50
・第一志望は偏差値60(2月1日と3日)
・第二志望以下はあまり決まっていない
・東京南部・神奈川近辺在住
まず、現段階で決まっている試験日程を当てはめます。
2月1日午前 第一志望校
2月1日午後
2月2日午前
2月2日午後
2月3日
2月4日 第一志望校(2次)
こんな感じでしょうか。
次に大切な視点が、早い段階で合格を掴むこと。つまり、早い試験日程で「安全校」をセットすること。
「安全校」とは、自分の持ち偏差値よりも少なくとも5以上下の学校をセットすることです。
特に定員が少なく、上位校の狙いづらい、試験日程が割と早い1日午後や2日午後に持ってくることをお勧めします。
上記のお子さんですと、いまのところの持ち偏差値が50ですから、45以下を中心に3校ほど回ります。
2月1日午前 第一志望校(SS60)
2月1日午後 安全校(SS40~45)この中で3校ほどリストアップ
2月2日午前
2月2日午後 安全校(SS40~45)この中で3校ほどリストアップ
2月3日
2月4日 第一志望校(2次、SS65)
こんな感じでしょうか。
タカベルではこの安全校さえセットしていただければ、あとはどこを受けていただいても大丈夫というスタンスです。毎年このスタンスを貫いています。
この安全校という考えは絶対に無視できません。
特に第一子さんをお持ちのご家庭に多いのが、偏差値の高い学校ばかりをセットする傾向です。
第一子様ですと親御さんも初めての受験。期待も高く、上位の学校を目指させたいという気持ちも大変理解できるのですが、入試期間中のプレッシャーは尋常ではありません。連戦連敗となったときのお子様のストレスは本当に過酷なものです。
うまくいかなかったケースも常に頭に入れておく必要があります。
上記のケースであればなおさらですが、第一志望の2次試験が4日に控えています。1日残念だった場合、プラスのメンタリティーで4日に向かわせることが極めて重要です。
しかし、これをセットいただければあとはどこでも構いませんので、極端な話、下記のようなパターンでも大丈夫です。
2月1日午前 第一志望校(SS60)
2月1日午後 安全校(SS40~45)この中で3校ほどリストアップ
2月2日午前 受験検討校(SS70)
2月2日午後 安全校(SS40~45)この中で3校ほどリストアップ
2月3日 受験検討校(SS70)
2月4日 第一志望校(2次、SS65)
上記はやや極端ですので、現実的プランは下記のようになるでしょうか。
2月1日午前 第一志望校(SS60)
2月1日午後 安全校(SS40~45)この中で3校ほどリストアップ
2月2日午前 受験検討校(SS50台後半)この中で3校ほどリストアップ
2月2日午後 安全校(SS40~45)この中で3校ほどリストアップ
2月3日 受験検討校(SS65) この中で3校ほどリストアップ
2月4日 第一志望校(2次、SS65)
まとめると、
・第一志望が定まっている場合、そこは受けることを想定する。
・2月1日午後・2月2日午後は安全校を中心に組む。(この見積もりは特に厳しく)
・学校見学の際は試験日程・偏差値という観点も忘れずに。
強気でいくなら、保険はしっかりかける。
受験の鉄則です。
最後に試験問題のかみ合わせという視点がありますが、特に5年生以下はまだ気にせずで大丈夫。6年生はプロに相談しましょう。
無料面談では、第一志望校との問題のかみ合わせのよい受験校相談や学校説明会で聞いておくべきポイントなども随時受付中。塾に通っている方も相談可能です。
2025年03月26日 19:39